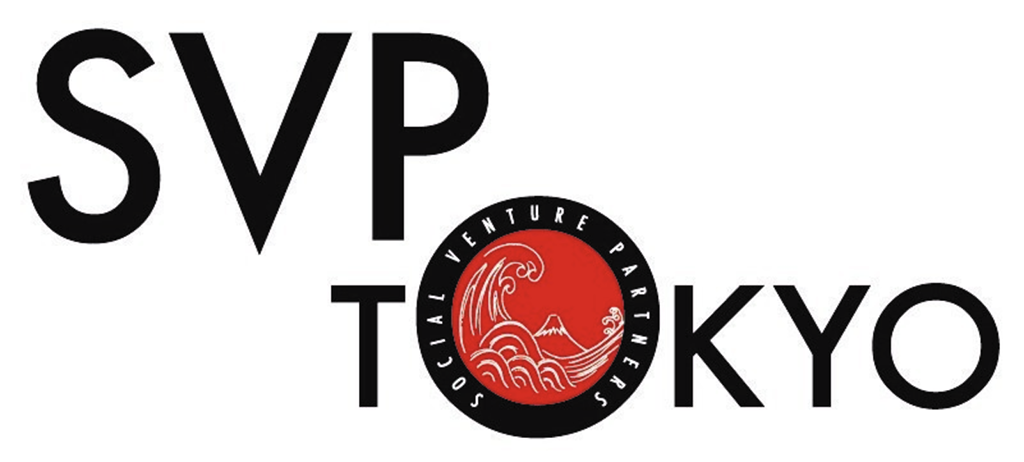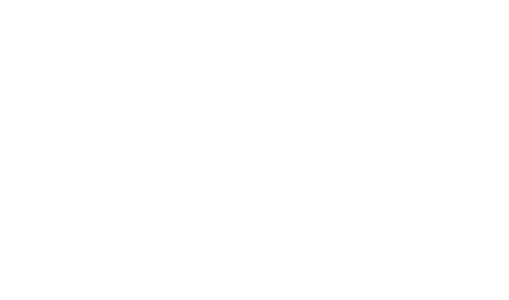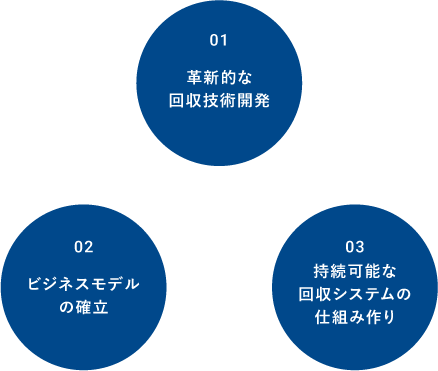
海洋ごみゼロの世界を目指して
長期的かつ持続可能な海洋資源利用の実現のため、革新的な回収技術開発やビジネスモデルの確立、海洋ごみ削減に向けた持続可能な回収システムの仕組み作りなどに取り組んでいます。

海上・海底・河川で放置されてきた
海洋ごみを回収する
漁網やフロートなど世界中どこにでも手軽に入手できる素材で作られた低コストの回収装置を活用し、海洋・河川・海底に放置されている回収困難な海洋ごみを効率的に回収。持続可能な方法で環境改善に貢献します。


海洋ごみ回収活動を見える化し、
インパクトを最大にする
世界中の海洋ごみ回収データをマップで可視化し、活動の成果を共有。企業や個人の支援を促し、より多くの海洋ごみ回収や再資源化を実現します。


海洋ごみを再資源化し、
資源循環の輪に戻す
回収した海洋ごみを選別・加工し、再利用可能な資源として再生。企業やクリエイターと連携し、新たな製品や素材に生まれ変わらせ、持続可能な循環型経済を推進します。

NEWS
ニュース








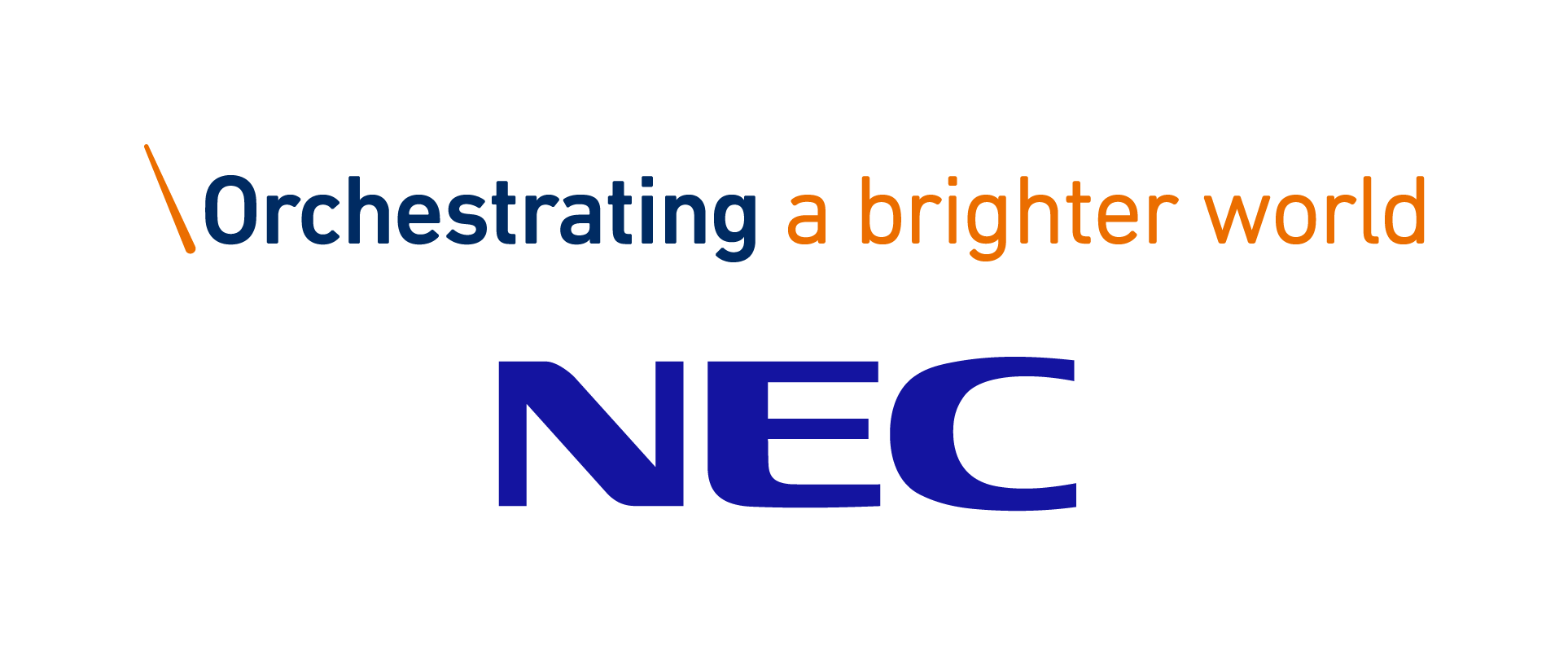

.png)